「発達障害特性がある人材の就労における能力発揮支援」のプロジェクトメンバーである京都大学 医学研究科/山田先生、日本総研/山内研究員に、プロジェクト参画までの軌跡、注目ポイント、実現したい社会について聞きました。
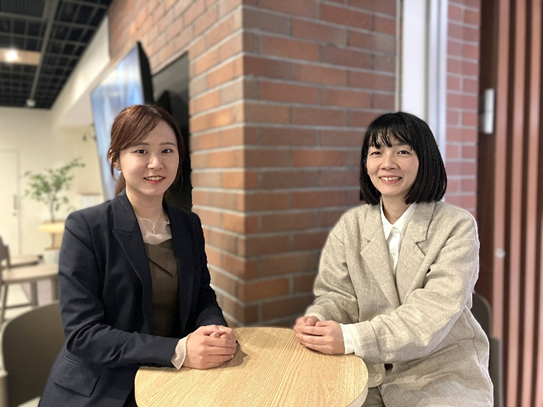
発達障害に関心をもったきっかけ・本プロジェクト参画への経緯を教えてください。
山田先生 私はもともとは文学部出身で、英語や古典が好きで日本の常識とは違う異文化に興味がありました。乳幼児の発達心理学について勉強するなかで自閉スペクトラム症に関する論文を読むこともあり、見え方・感じ方の違いに関心を持ちました。その後、臨床の現場に携わりたいとの思いから医学部へ進学し、病院・診療所で児童を中心とした発達障害特性のある方の診療に携わってきました。成人の患者さんからの、なかなか仕事で上手くいかないがどうしたらよいか等の相談は多いです。また、幼少期から診ていた患者さんが、就労してからの継続に苦労している、といった話も聞きます。就労の問題に自分としてどのようにアプローチできるかと考え、就労にフォーカスした本プロジェクトへの参画を決めました。
山内研究員 私は生命理工学部出身でがん細胞に関わる研究をしておりました。また、個人的にはスポーツ科学の勉強・実践もしていました。日本総研へ入社してからは介護関連のプロジェクトに携わっておりましたが、福祉分野という共通点から発達障害に関連するプロジェクトに関わらせてもらいました。実は今回のプロジェクトの前身として、北海道小樽市のプロジェクトもあり、発達障害特性のある小中高生向けにボクセルアート(*)を作成できるPCゲームの講座を実施しました。その現場で、子どもたちの作業の覚えの早さ・作品のクオリティの高さに驚き、社会での活躍の可能性を感じました。題材にしたボクセルアートゲームを仕事にしている人もおり、単に遊びでなく、仕事に繋がる可能性を子どもたち・保護者に伝えることができました。これをきっかけに発達障害に関してもっと何かできることはないかと考え、現在のプロジェクトにも参画することになりました。
(*)立方体を組み合わせて作成する3D作品。
本プロジェクトの注目ポイントを教えてください。
山田先生 私が発達障害特性のある方と接するのは病院の診察室であり、患者さんの生活のごく限られた場所に留まります。今回のプロジェクトで着目する就労は、より生活に近く、そこにアプローチできることに新鮮さを感じています。また、いつもは医療従事者と関わることが多いのですが、本プロジェクトでは様々な方とつながり、立場による発達障害への理解や視点の違いを知ることで刺激をもらっています。

山内研究員 シンクタンクとしても、今回のプロジェクトで臨床に携わられる義村先生・山田先生、そのほか多くの方々から現場に近い声を聞けることは貴重な機会です。また、普段のコンサルティングの業務より手探りで、まさに研究からスタートしていると感じます。メンバー同士が組織の垣根を超えて自由に意見を交わしながら、チャレンジングですが、楽しく進められています。
山田先生 確かに、割と考えたことをなんでも言い合える関係性ができていますね。期間もしっかりあるので、深く考えていけるプロジェクトだと思います。
本プロジェクトを通して実現したい社会を教えてください。
山内研究員 発達障害特性のある方の雇用機会をもっと増やし一般就労の方々と同じように企業の利益に貢献できるような社会にしていきたいです。しかし、発達障害特性のある方に過度な配慮をしてしまうと、周りで働く人々は不公平を感じることもあります。だから、発達障害特性のある方をただ特別扱いするのでなく、得意・不得意が大きいと捉え、得意を活かし、不得意をカバーする方法を一緒に考えるのが良いと考えています。合理的配慮の範囲内で、一緒に働きやすい人間関係、職場の雰囲気になれば、全体としても過ごしやすい社会になると思います。

山田先生 山内さんの話にも繋がりますが、うまく頼り合える社会になればと思います。医師としてさまざまな方と接する中で、発達障害特性のある方に限らず、人に上手く頼る力が大切だと感じます。例えば仕事の場面では、自分が苦手なことでも、案外、人に聞いてみると全く苦でなかったりします。また、多くの人にとっては苦手なことが、自分はむしろ得意ということもあります。就労においては、一人でできるように自立することが求められることが多いかと思います。しかし、できないことに注目して、克服を目指すやり方は上手くいかないことも多く、克服しろと言われる側も非常に負担を感じます。このプロジェクトを通して、もっと、お互いに頼りあえる社会に近づくヒントを得られればと思います。


