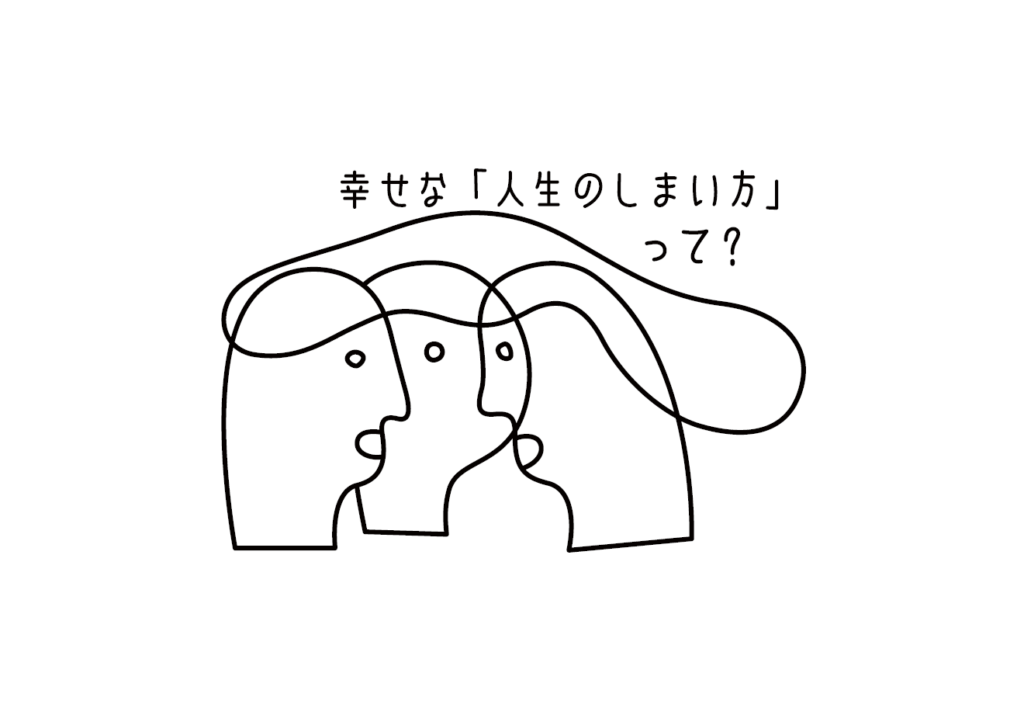「誰もが生前・死後の尊厳を保つための持続可能な身じまい・意思決定とその支援」のプロジェクトで、高齢期の身じまいに関する備えや、考え方に関するアンケート調査を行いました。
はじめに
皆さんは、ご自身の高齢期や、いずれやってくる最期に備えて、準備していることはありますか。あるいは、皆さんの高齢の家族が、身じまいについてどのような希望を持っているのか、人生の最期をどのように迎えたいと思っているのか知っていますか。
万が一のことがあったとき、特に高齢期の場合には、肝心の本人に意識がなかったり、認知機能が落ちてしまったりして、自分の希望を伝えられなくなってしまうことも考えられます。そのため、前もって必要な情報を整理してキーパーソンと共有するなど、いざというときに備えておくことが必要だと考えられます。とはいえ、いつ来るか分からない事態に備えるというのは難しいものですよね。とりわけ、自分や大切な家族の死に関することとなると、その重大さと考えておくべきことの多さに、一層腰が重くなるかもしれません。
実際のところ、自分の高齢期やいざというときに備えて、身じまいをしている人はどのくらいいるのでしょうか。また、高齢期への備えや人生のしまい方について、人々はどのような希望や心配事を持っているのでしょうか。今回、私たちは、40代以上の方を対象にアンケート調査を行い、人生の身じまいについての考え方や、備えの状況について調べました。
アンケート調査の概要
調査方法:インターネットによるモニター調査
調査実施期間:2025年1月30日~2025年2月1日
調査対象:40代以上の男女
回収状況:下記表の通り
図表1.割付・回収状況
| 割付 | 目標数 | 回収数 | 回収数全体に占める割合 | |
| 男性 | 40代 | 125 | 129 | 12.5% |
| 50代 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 60代 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 70代以上 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 女性 | 40代 | 125 | 129 | 12.5% |
| 50代 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 60代 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 70代以上 | 125 | 129 | 12.5% | |
| 合計 | 1,000 | 1,032 | 100% |
アンケート調査の主な結果
ここからは、アンケート調査の主な結果をご紹介します。
その1.身じまいについて備えていること
「身じまいについて「特に備えていることはない」人は70代でも約45%」
いざというときに備えて身じまいをしている方はどのくらいいるのでしょうか。また、実際にどのような身じまいをしているのでしょうか。
アンケート調査の結果をみると、60代以下では、70%近い人が「特に備えていることはない」と回答しました。70代以上でも、「特に備えていることはない」と回答した人は44.6%にのぼり、実際に行動に移している人は半数程度にとどまりました。
他年代に比べて備えを行っている割合が高い70代について、どのような身じまいをしているかをみると、重要な書類の保管場所を家族に共有することが34.5%で最も多い結果となりました。また、より先の未来を想定して、エンディングノートを作成したり、家族と医療・介護や葬儀、相続などについて事前に話し合ったりしている人も20%弱みられました。
図表2.身じまいについて備えていること:複数回答

その2.万が一のときに頼れる相手
「万が一のときに頼れる相手は、60代以下では配偶者・パートナー、70代以上では子・子の配偶者」
いざというときに頼れる相手についても尋ねました。「引っ越しの際の身元保証人」、「在宅介護サービスでの同居人以外の緊急連絡先」、「高齢期の入院時の身元保証人」、「手術の同意」、「将来の医療・ケアについての話し合い」など、10個の場面で実際に誰に頼ることができるかを聞きました。
10個の場面の回答を積み上げてみると、60代以下では「配偶者・パートナー」と回答した人が最も多くなっていました。一方、70代以上では、「子・子の配偶者」が70%強で最も割合が高く、「配偶者・パートナー」は50%弱にとどまりました。高齢期になると、配偶者やパートナーもケアが必要な立場になっていたり、離別していたりで、万が一のときに頼ることが難しくなるといった事情がうかがえました。
また、70代以上で誰に頼れるか「分からない」と回答した人や、誰かに「頼るのは難しい」と回答した人が20%弱にのぼりました。子どもが遠方に住んでいる場合や、身寄りがない場合など、頼れる人がいない高齢者をどのようにサポートしていけばよいのか、早急に検討する必要があるでしょう。
図表3.【積み上げ】実際に頼れる相手:複数回答

その3.身元保証サービスを利用することへの考え
「身元保証サービス事業者の良し悪しを懸念する人が2割前後」
身近に頼れる家族などがいない場合には、民間の身元保証サービスを利用することも一手ですが、アンケート調査では、事業者の良し悪しが判断できないことや、事業者の質が悪い場合に家族に迷惑をかけてしまうことを懸念して、利用を躊躇すると回答した割合が2割前後にのぼりました。身元保証サービス事業者の評価や、サービスを監督する仕組みの必要性が示唆されました。
また、身元保証サービスの利用には比較的若い世代の方が強く関心を示す傾向があり、40代では20%強が「利用する金額が高くなければ、使ってみたい」、「家族などに負担をかけず、良い思い出となる時間を増やせるよう、サービスを利用したい」と回答しました。
図表4.身元保証サービスの利用についての考え:複数回答(最大3つ)

その4.高齢期の身じまいについての望みと心配事
「70代では「終活」をしたい人が3割強」
最後に、アンケート調査の回答者が高齢期の身じまいについて、どのような望みや心配事を持っているのかをご紹介します。
まず、高齢期の身じまいについての望みは、すべての年代で、「家族や友人との時間を大切にし、感謝を伝え、思い出を共有すること」を選択する割合が最も高く、60代以下では50%前後、70代以上では60%弱でした。また、70代以上では、「金銭管理や資産の整理を行い、家族に負担をかけないようにすること」と回答する割合も50%強にのぼり、家族に配慮した身じまいを希望していることが分かりました。
さらに、70代以上では、「自分の最後をどのように迎えたいかを考え、エンディングノートや遺言書の作成、葬儀の準備をする」といった、いわゆる「終活」をしたいと考えている人も30%強みられました。
図表5.高齢期の身じまいについての望み:複数回答(最大5つ)

一方、高齢期の身じまいに関する心配事について、40代、50代では、年金や貯金で生活費や医療費をまかなえるのか、老後資金への不安を感じている人が5割以上みられました。70代以上になると、家族に介護負担をかけることや、認知症などで判断能力が低下して物事を決められなくなることに不安を感じている人が5割強にのぼり、他の年代に比べて高くなっていました。
高齢期に判断能力が低下してしまうと、身じまいも難しくなる可能性があります。終活をしたいと考えている人がタイミングを逃さずに終活に取り組むことができるように、どのような支援が必要なのか検討する必要があると考えます。
図表6.高齢期の身じまいについての心配事:複数回答(最大5つ)

おわりに
今回のアンケート調査を通して、40代以上の方が高齢期の備えや身じまいにどのように取り組んでいるのか、どのような考えを持っているのかを、垣間見ることができました。特に、40代~60代の7割弱、70代以上の4割強の人がいざというときの備えを全くしていない、という結果は、本プロジェクトに重要な示唆を与えてくれているように思います。いずれ来ると分かっていながら、老いや最期にむけた身じまいが難しいのはなぜなのか、どうすれば幸せな身じまいができるのか、引き続き調査を進めます。
以下の報告書では、上記で紹介できなかったものを含めて結果をまとめていますので、詳細を知りたい方はぜひご覧ください。