
酵素を活用したどこでも誰でも使える
CO₂資源化技術の開発・実装
プロジェクト内容
取り組む社会課題
人類の存亡に関わる最重要課題「CO₂削減」に挑みます。産業革命以降、大気中のCO₂濃度は増え続け、このままでは今後20年で気温が1℃上昇するとの予測もあります。2050年までにCO₂排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラル、そしてその先を見据えたカーボンネガティブ(*1)な社会の実現が望まれています。
現在、CO₂の回収・利用・貯留を行う技術(CCUS技術)が世界中で開発されています。しかし、既存のCO₂利用技術の多くは、CO₂を資源化するのに高温や高圧の反応条件が必要で、大量のエネルギーを消費します。このため、CO₂を排出しないエネルギー源を大量に確保することが大きな課題です。また、CO₂を地下に貯留する技術は、CO₂貯留による環境リスクが完全に解消されているわけではなく、根本的な解決策として疑問視する声もあります。
私たちは、既存のCCUS技術が抱える「高温高圧」と「エネルギー消費」という課題に対し、ユニークなアプローチで挑みます。
(*1) CO₂の吸収量が経済活動によって排出されるCO₂の排出量を上回る状態を指します。CO₂の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」よりもさらに強化された取り組みといえます。
アプローチ
物質循環の視点から、持続可能なCO₂資源化技術を開発し、世界のCO₂削減に貢献します。具体的には、電気を流す特別な酵素と、ガス拡散型電極を組み合わせることで、常温・常圧・中性の環境で、空気中のCO₂を電気の力で別の物質に変える技術を開発しています。この技術は「どこでも・誰でも使える」という大きな特長を持ち、安全かつ身近な脱炭素ソリューションとして広く普及させることを目指します。
この技術でCO₂をバイオ資源化することで、メタン発酵や醸造、人間の呼吸など、日常生活で発生するCO₂も回収できます。これらのCO2排出量は、日本国内で年間5,000万トン(*2)と推定されており、これは2050年に回収すべきCO₂量の約4分の1に相当します。
再生可能な酵素と持続可能なエネルギーで動くこの技術は、CO₂から新しい製品をつくるバイオものづくりと組み合わせることができます。CO₂の資源化から製品化までを一貫して行うことで、真のカーボンニュートラルに向けた社会変革を実現します。
(*2)出典:①経済産業省(2021)_2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略、②NEDO(2020)「CO₂分離・回収技術の概要」
本プロジェクトで行うこと
- 低濃度CO₂回収機能電極の開発
- 気相CO₂の生物電気化学的資源化の事業化検討
- 2050年以降の持続可能な社会に向けた基盤構築



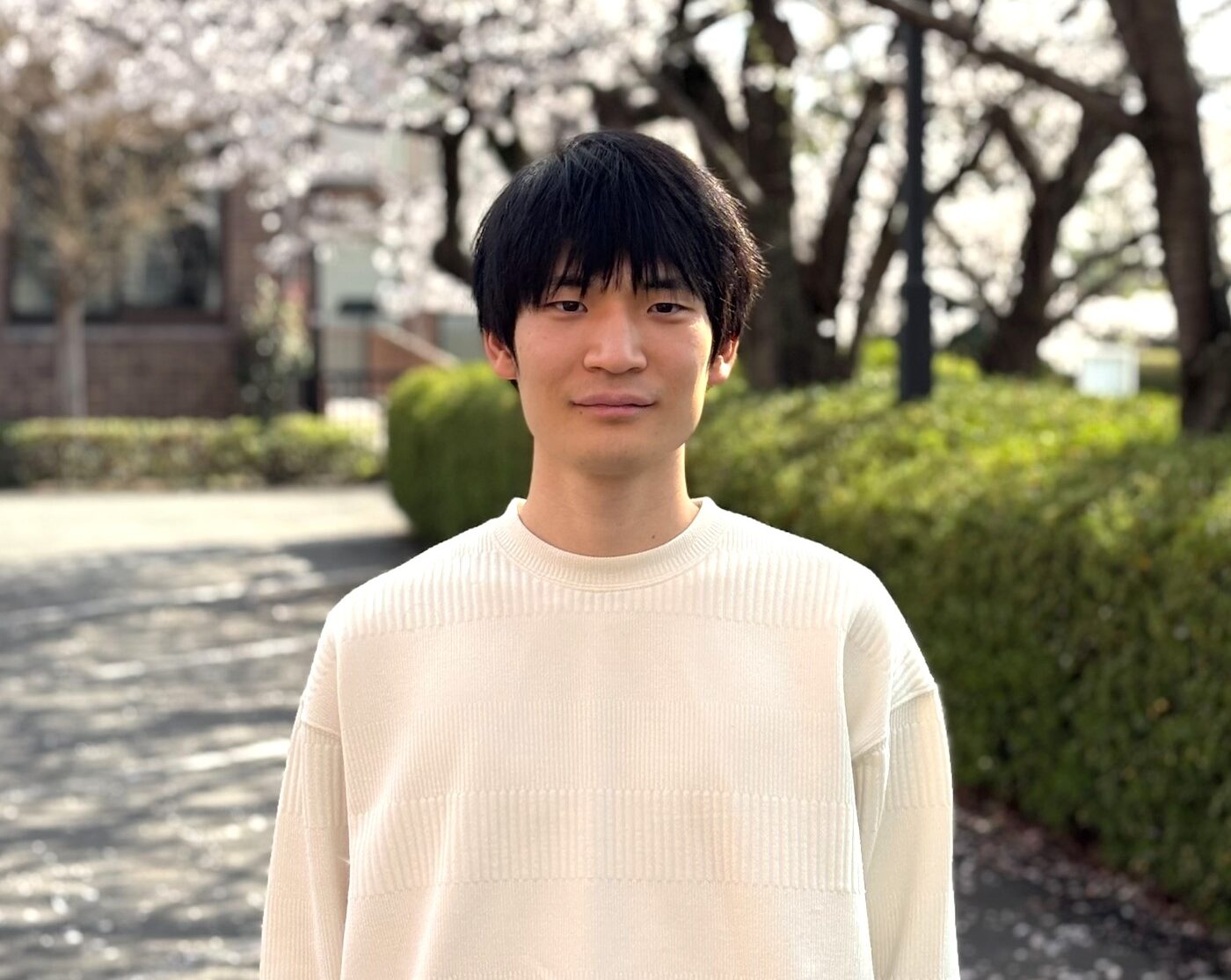




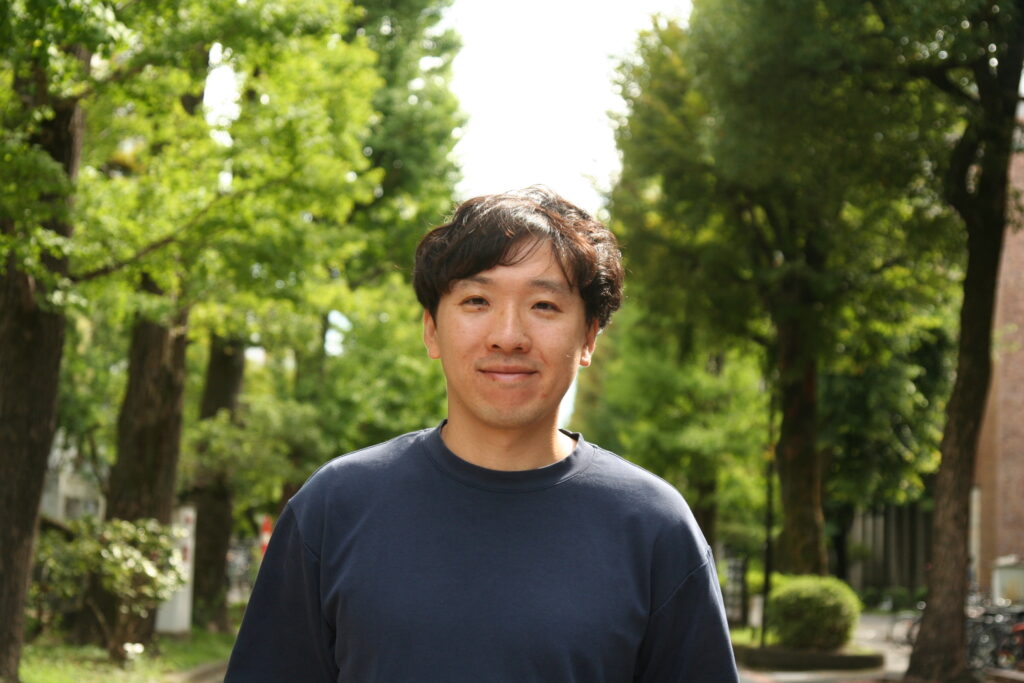
酵素の力を活用し、常温・常圧でCO₂を資源化することで、どこでも誰でも使える持続可能な脱炭素社会の実現を目指します。